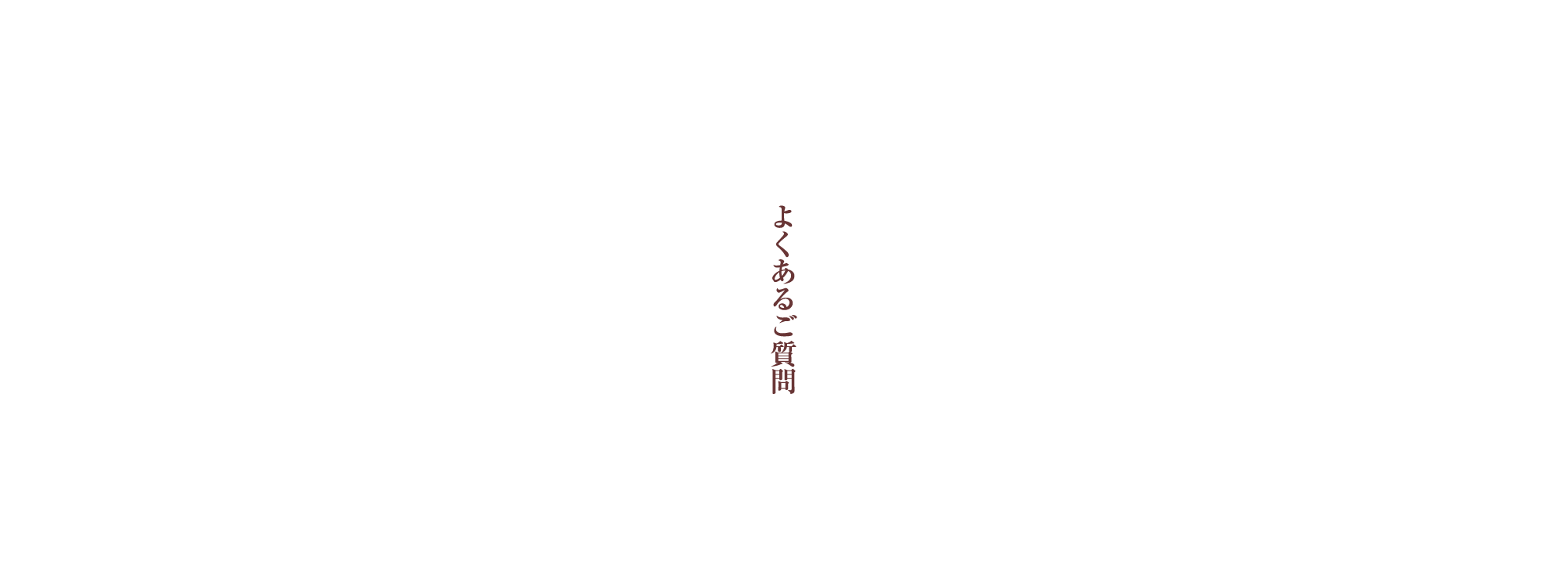
カテゴリー別アーカイブ: 余談
ハロウィン(余談)
ハロウィンは10月31日に祝われる行事で、もともとはケルト人の古代祭り「サウィン」が起源です。この祭りでは、収穫の終わりと冬の始まりを祝うと同時に、亡くなった人たちの霊が帰ってくると信じられていました。現代では、ハロウィンは主にアメリカやカナダで楽しまれていますが、世界中で人気が広がっています。
現代のハロウィン
- 仮装: 子どもも大人もさまざまなキャラクターに扮装します。魔女や吸血鬼、スーパーヒーローなどが定番ですね。
- トリック・オア・トリート: 子どもたちが近所を回り、「Trick or Treat!」と言ってお菓子をもらう伝統があります。これを訳すと「お菓子をくれないといたずらしちゃうぞ!」になります。
- ジャック・オー・ランタン: かぼちゃをくり抜いて作るランタンで、内側にロウソクを入れて灯します。これも古代ケルトの伝統から来ています。
日本でも最近ではハロウィンのイベントやパレードが増え、特に若者の間で仮装やパーティーが盛り上がっていますね。





