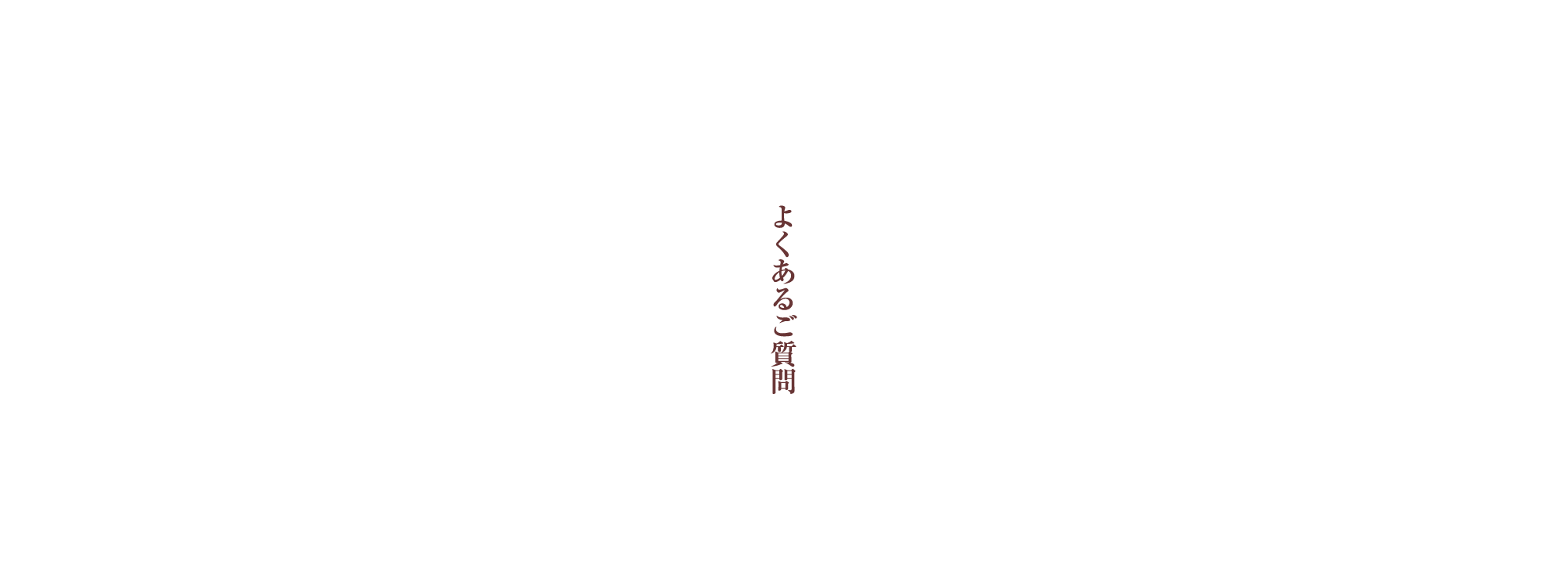
カテゴリー別アーカイブ: 日記
4月(卯月)
卯月(うづき)は旧暦の4月を指す言葉で、現在では新暦の4月の別名として使われることが多いです。その由来にはいくつかの説があります。
・卯の花が咲く月:アジサイ科ウツギ属の植物に咲く花「卯の花」が由来とされています。
・十二支の卯:十二支の4番目である卯(うさぎ)が4月にあてはめられたという説
・稲作の始まり:稲を植える月を意味する植月(うゑつき)や種月(うづき)が転じたという説
・万物の始まり:農耕が始まる月であることから、「産む」や「初ぶ」の「う」が由来とされる説
また、卯月には「夏初月(なつはづき)」や「初夏(しょか)」などの別名もあります。旧暦では4月が夏の始まりとされていたため、これらの名前が付けられています。





