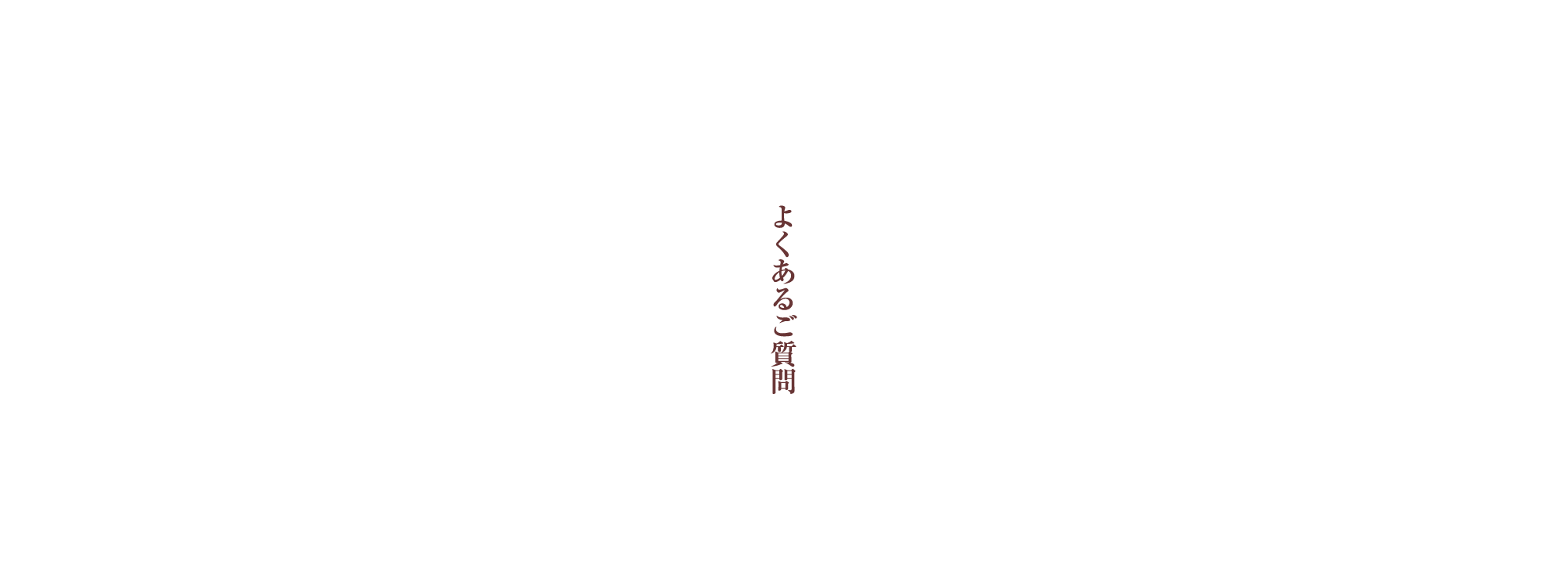
花まつり
花まつり・灌仏会(かんぶつえ)とは、華やかな花御堂に安置された誕生仏に甘茶をそそぐことで仏を供養し、子供たちの健康を祈る仏教行事のこと。一般的に、お釈迦様生誕の日とされる4月8日に行われます。この記事では、花まつり・灌仏会について紹介します。
花まつり・灌仏会とは、お釈迦様の誕生祝う仏教行事のこと。キリスト教でイエス・キリストの誕生を祝うのがクリスマスであるのと同じで、仏教ではお釈迦様の誕生を祝うのが花まつり、ということになります。「花まつり」として知られるお祭りの正式名称は、「灌仏会(かんぶつえ)」“仏に灌(そそぐ)”ことから「灌仏会」と名付けられ、降誕会(ごうたんえ、仏生会(ぶっしょうえ)、浴仏会(よくぶつえ)、竜華会(りゅうげえ)、花会式(はなえしき)とも言われます。
この日のために作られた小さな御堂(※仏像を安置した堂のこと)である花御堂に、右手で天を指し左手で大地を指した誕生時のお釈迦様をかたどった彫像・誕生仏(たんじょうぶつ)を安置します。これは華やかな色や香りを持つ花によって仏を供養するという意味があり、花御堂は色とりどり華麗に飾られます。仏が歩く道に花をまく散華(さんげ)と呼ばれる行いになぞらえたものです。
花御堂に安置された誕生物に、参拝者が甘茶をかけます。こうすることで、体を洗い清め、子どもの身体健全や所願の成就を願います。甘茶をかけることは、昔虫よけやまじないにも使われたそう。花まつり中、お寺によっては甘茶をふるまってくれることもありますが、そもそも甘茶って何?と思う方も多いでしょう。甘茶とはアマチャの基から作られた、独特な甘さの有るお茶のこと。
お寺によって、白い象の置物が登場することがあります。おおきさはさまざまで、大きな象の背中の上に花御堂を乗せていることもあります。白い象が神聖な動物として扱われている理由は、お釈迦様の母である摩耶夫人が「夢の中で六本の牙を持つ白い象を見た」ことでお釈迦様を懐妊したと言われていることから。白い象がお釈迦様を運んできた、と信じられていることに由来しています。また、白い象は雨を表し、五穀豊穣を意味するとも言われています。
4月(卯月)
卯月(うづき)は旧暦の4月を指す言葉で、現在では新暦の4月の別名として使われることが多いです。その由来にはいくつかの説があります。
・卯の花が咲く月:アジサイ科ウツギ属の植物に咲く花「卯の花」が由来とされています。
・十二支の卯:十二支の4番目である卯(うさぎ)が4月にあてはめられたという説
・稲作の始まり:稲を植える月を意味する植月(うゑつき)や種月(うづき)が転じたという説
・万物の始まり:農耕が始まる月であることから、「産む」や「初ぶ」の「う」が由来とされる説
また、卯月には「夏初月(なつはづき)」や「初夏(しょか)」などの別名もあります。旧暦では4月が夏の始まりとされていたため、これらの名前が付けられています。





