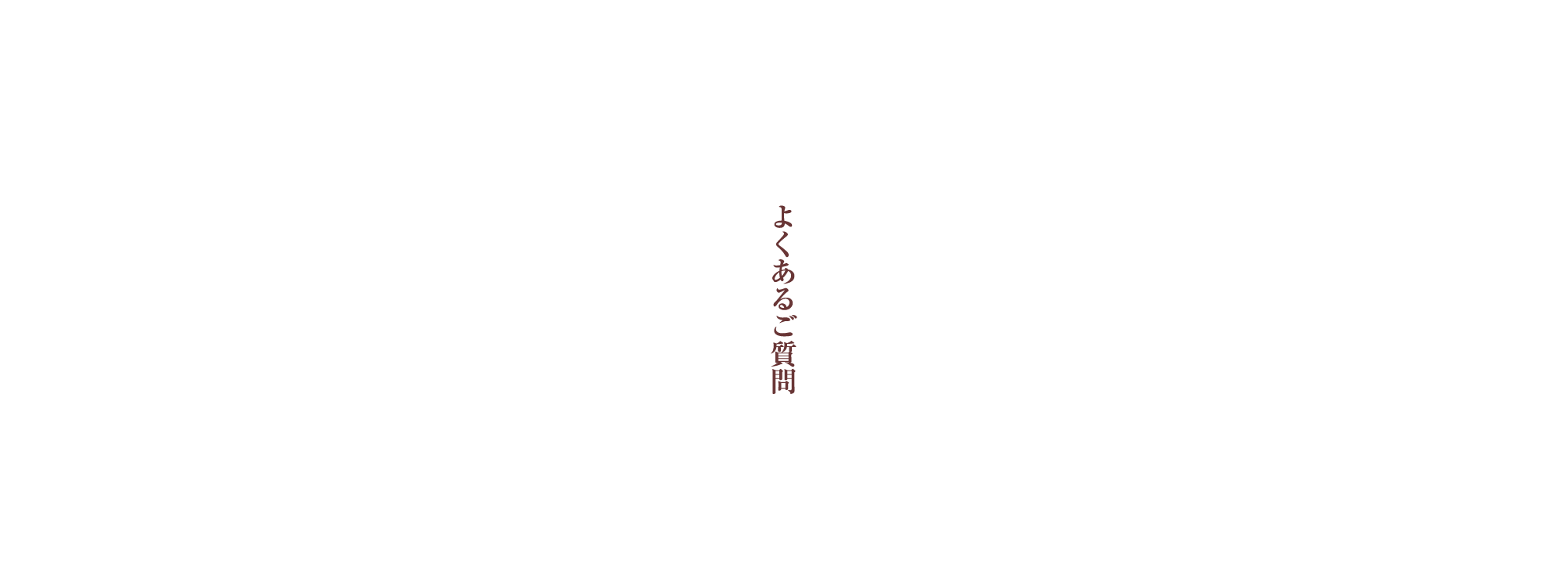
通夜振舞い
通夜振舞い(通夜ふるまい)とは、通夜の後に行われる会食の場です。別室に用意されたお酒や食事を皆で囲みながら、故人を偲んで思い出を語り合います。遺族から参列者への感謝を表すとともに、お清めや故人の最後の食事といった意味も含まれる儀式です。お通夜は、予定の方が急に来れなくなったり、反対に思ってもみない方が参列に来られたりと、人数の把握がしづらいものです。予定人数に多少の増減があっても対応しやすい様、お通夜の席の食事は大皿(寿司桶やオードブルなど)で用意しておくのがおすすめです。参列者側としてはご遠慮もあり、なかなか席に付きにくいので葬祭スタッフだけでなく喪主や近親者が協力してお席へご案内すると良いでしょう。又、同じ種類のお料理で各席を揃えておくと参列者の方々も箸を進めやすいかもしれません。
六曜その2
さて、葬儀に関係がありそうな「仏滅」と「友引」についてです。
仏滅(ぶつめつ) 「仏が滅するような」大凶日とされています。「滅びることは新たなスタートに結びつく」という前向きな解釈も存在します。一見、葬儀には不適当なイメージですが、中国の占い由来ということからも仏教には何の関わりもなく、仏滅だからといって葬儀や法事を避けるという考え方はありません。
友引(ともびき) もともとは勝負事が引き分けになる日とされてきましたが、意味が転じ「友を引き寄せる」として幸せのおすそ分けに適した日と考えられるようになり、友引に合わせて結婚式の引出物を贈る人もいるようです。ただし葬儀では、この「友を引き寄せる」という意味が、親しい人を冥界に引き寄せるという事を連想させるため、昔から友引でのお葬式は避けられてきました。尼崎市では原則として友引は火葬場自体が休場日になっており、お葬式を執り行うことはできません。(不定期で開場日あり)
香典
●仏式の場合●
葬儀時から満中陰までは上段中央に「御霊前」とそれ以降は「御仏前」と書きます。
ただし、亡くなると同時に仏になる浄土真宗の場合は満中陰前、葬儀から「御仏前」と書きます。
又、上記他には「御香典」や「御香料」等があります。
.
●神式の場合●
銀の水引(無ければ黒白でも構いません)を使います。表書きは「御玉串料」と書きます。「御神前」または「御榊料」と書くこともあります。
蓮の柄がついた香典袋を時々見かけますが、神式には使えません。
.
●キリスト教の場合●
水引は無くても構いません。表書きは「献花料」や「御花料」と書きます。
.
.
■住所・氏名・金額について
中袋には喪家が香典の整理をする際に重要な資料になりますので、住所・氏名・金額をはっきり書きましょう。
グループで包む場合は半紙などにメンバー全員の名前を書き中へ入れます。
表書きは「○○会有志」とか「○○会社営業部一同」のようにグループ名称のみ書きます。
.
■香典を郵送する場合
通夜・告別式とも出席出来ないときには現金書留で香典を郵送します。
この場合まず、現金を香典袋に入れてから現金書留の封筒に入れます。
その際には出席出来ない理由と、故人を偲ぶ手紙を添えると心がこもるでしょう。
.
■香典の備え方
香典を霊前に直接供えるときは、自分の方から読めるよう(霊前に対して逆向き)に供えます。
受付で渡す場合は、相手から読めるように渡します。





